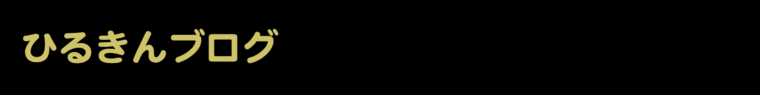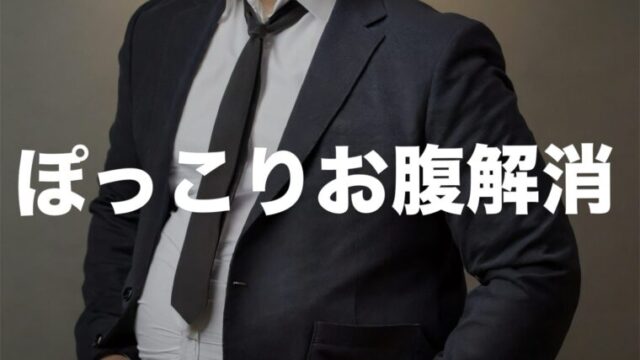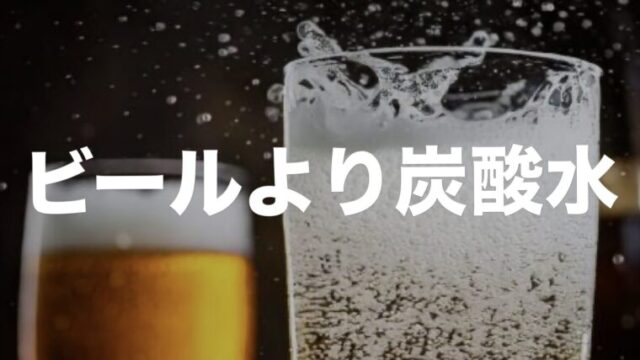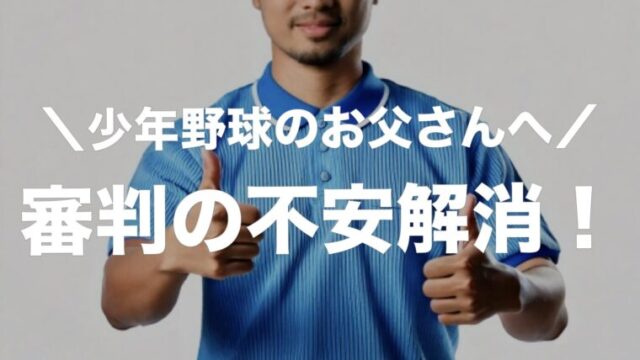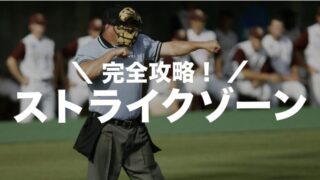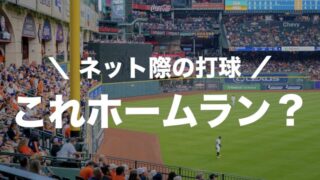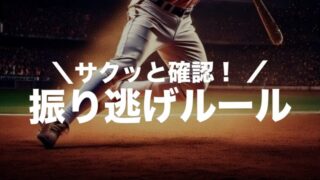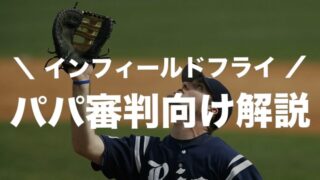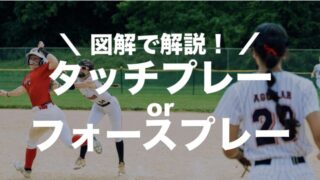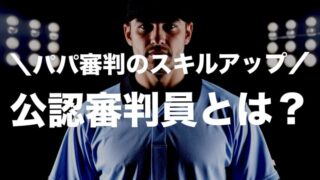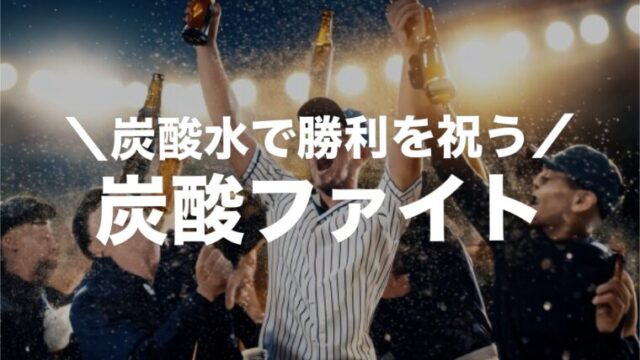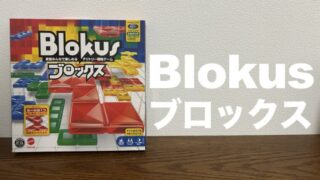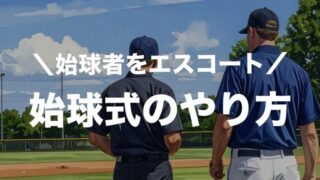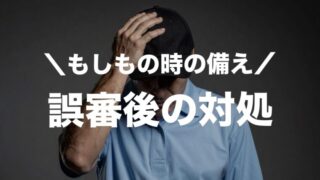野球の始まりは「ゆるスポーツ」?笑える20の原点ルールを紹介!
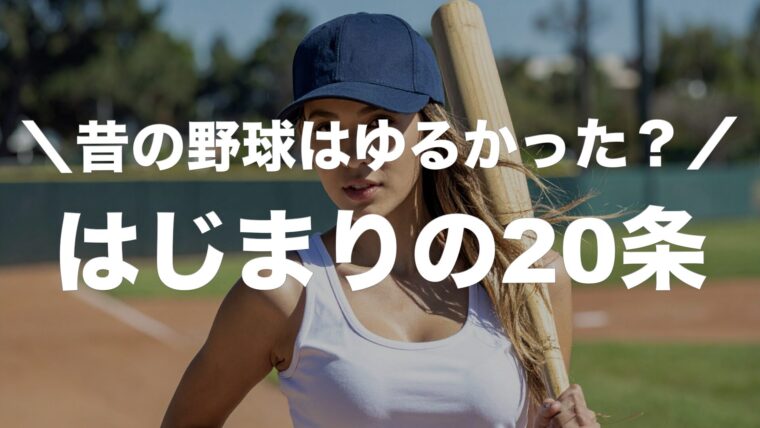
野球って、いつからあると思います?
実は、最初のルールが作られたのは1845年。今から約180年も前のこと。
その頃の日本は江戸時代の末期にあたりますが、当時の「野球規則」は、意外と今の野球と通じるところが多い!そして、どこかちょっと「ゆるい」笑
この記事を読めば、お父さん同士の話のネタが増えるはず。審判をしている方なら知っておいても損はありません。
それでは、180年前の野球ルールを、“少年野球パパ目線”で読み解いてみましょう!
この記事は、当時のルールを筆者の感覚で”ゆるく解釈”したものです。正式な正式な資料としてではなく、「こんな解釈もあるんだな〜」程度に野球のルーツを楽しく知るための読み物としてお楽しみください。
\この記事を書いた人/
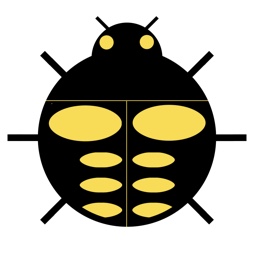
ひるきん
小学校から大学まで野球を続けた経験を持つアラフォーパパ。わが子も少年野球を始めたことがきっかけで、審判としてグラウンドに立つ機会が増えました。しかし、そこで気付かされた「野球のルール、ちゃんと分かってない…」。わが子とともに日々野球の勉強中です!
>>さらに詳しいプロフィールを見る
\こんな記事も書いています/
- 第1条 遅刻はアカン!
- 第2条 審判はちゃんと決めるで!
- 第3条 メンバーと攻守はキャプテンが決めるで!
- 第4条 塁間は歩幅で決めるで!
- 第5条 練習日はちゃんと練習!
- 第6条 メンバー足らんかったら助っ人OK!
- 第7条 キャプテンがええなら途中参加OKや!
- 第8条 21点取ったもん勝ちや!
- 第9条 打ちやすいボールを投げてな!
- 第10条 ホームランはファールや!
- 第11条 三振でもボール落としたらチャンスや!
- 第12条 フライもワンバン捕球もアウトやで!
- 第13条 走者はボールタッチでアウトや!
- 第14条 守備を妨害したら即アウトや!
- 第15条 スリーアウトでチェンジや!
- 第16条 打つ順番は守らなあかんで!
- 第17条 審判が絶対や!
- 第18条 ファールは何もできまへん!
- 第19条 ボークすな!
- 第20条 エンツーはあるで!
- まとめ|“遊び心”から始まった野球のルール
- おまけ|参考書籍
第1条 遅刻はアカン!

第1条 メンバーは決められた時間通りに集合すること。
引用元:野球審判員マニュアル
今も昔も、「時間厳守」は野球の基本中の基本。第1条からルールとして書かれているということは、180年前から遅刻は許しがたい行為であったということ。
昔の人も“集合遅れる人”がいたってことなんでしょうね。
第2条 審判はちゃんと決めるで!

第2条 メンバーが集合した時、会長(会長が不在の場合は副会長)は審判を指名する。審判は試合を記録用のノートに記録し、この規則に違反したすべての行為を書き留める。
引用元:野球審判員マニュアル
少年野球でもありますよね、「今日は誰が審判?」とか「またパパ審判足りてない!」といった場面。審判を指名することが、きちんとルールで定めているところが、180年前から審判の重要性が認識されていた証です。
しかも違反があれば、ノートにメモしなくてはいけません。現代のスコアブックの元祖なのかもしれませんね。
\審判に自信のないパパにオススメ/
第3条 メンバーと攻守はキャプテンが決めるで!

第3条 会長(会長が不在の場合は副会長)は2人のメンバーをキャプテンに指名する。2人はその場を離れて相談し、試合に参加する選手を選ぶ。その際、両方の選手の技量ができるだけ同じになるように留意する。キャプテンは率いるチームをコイン・トスで決め、次に同じ方法で先攻を決める。
引用元:野球審判員マニュアル
昔は、監督ではなく、キャプテン同士でメンバー決めていたんですね。まるで「紅白戦の選手決め」みたいで、親近感ご沸きます。
両チームの技量が同じになるように選んでいたところも、当時は“野球を楽しむ”ことを重視していたのでしょう。
ちなみに、どちらのチームになれるかや先攻後攻は、運次第。“コイントス”でを決めるってところが、サッカーみたいで新鮮です。
第4条 塁間は歩幅で決めるで!

第4条 塁と塁との距離は、本塁から二塁まで42歩、一塁から三塁までが42歩で同距離とする。
引用元:野球審判員マニュアル
塁間は“42歩”!ヤードでも、メートルでもなく、“歩”っ!「歩いて測る」というアナログさが、時代を感じます。
成人男性の歩幅をだいたい70cmとすると、ホームから一塁までの間は約21m。今の少年野球の塁間23m前後に比べて、少し短い。内野ゴロをさばくのが難しそうです。
「足の長い人が測ったら、ちょっと遠くなるやん!」とツッコミたくなりますが、きっと当時は、それくらいおおらかだったのでしょう。
第5条 練習日はちゃんと練習!

第5条 通常の練習日には、対外試合は行わない。
引用元:野球審判員マニュアル
楽しい試合ばっかりしててもダメ!「ちゃんと練習はしなはれ!」というところが、技術面も大切にしていたところが伺えます。
試合はもちろん大事ですぎ、上手くなるには「地味〜な反復練習が欠かせまへん!」てところが昔も今もかわりません。
第6条 メンバー足らんかったら助っ人OK!

第6条 練習開始時間にクラブのメンバーが足りない場合には、メンバー以外の人を選手に加えることができる。メンバーが後から現れても練習に参加させる必要はない。ただし、選手を選ぶ際にその場にいれば、いかなる場合でもメンバーに優先権がある。
引用元:野球審判員マニュアル
助っ人OKとか、おおらかな感じがいいですね!「人はおらんけど、練習はやろか!」というノリが伝わってきます。
ただ「メンバーが後から現れても練習に参加させる必要はない」とか、遅刻者には超厳しい!1845年のクラブ運営、締めるところは締めてます。
第7条 キャプテンがええなら途中参加OKや!

第7条 試合開始後にメンバーが現れたときは、両キャプテンがお互いに同意すれば、選手に加えることができる。
引用元:野球審判員マニュアル
遅刻してきた選手も、「どうしても出たい!」って気持ちがあればチャンスあり。ただし、キャプテン同士が“まぁええか”って言うたらOKという、人情味あるルールがいいですね。
「みんなで楽しむのが一番」という空気感も心地良い。こういう柔らかさが、野球が長く愛されてる理由かもしれません。
第8条 21点取ったもん勝ちや!

第8条 試合は21点で成立する。ただし、試合終了時に両チームのアウト数は同じであること。
引用元:野球審判員マニュアル
なんと、21点先取で試合成立!まるでバレーボールみたいなルールです。
「両チームのアウト数は同じであること」ってのがミソ。「21点取ったしもう終わりや!」じゃなく、きっちり裏のチームにもチャンスを与えるとか、勝負のフェアさを大事にしてたんでしょうね。
それにしても21点って…今の野球で考えたら、どんな打撃戦!?
第9条 打ちやすいボールを投げてな!

第9条 打者に対する投球はピッチで、スローではない。(注:投手は下手投げで打者が打ちやすいボールを投げていた)
引用元:野球審判員マニュアル
今みたいに「打ち取ってやる!」って時代ではなかったようですね。どうりで「21点選手で試合成立」のルールがあるはずです。
当時のピッチャーは、“勝負する相手”というより、打者を立てる人。「ちゃんと打ちやすいとこに投げまっせ〜!」がモットーです。
“みんなで楽しむ野球”の原点がココにある感じがします。
\ストライクは打者への「打てよ!」/
第10条 ホームランはファールや!

第10条 打球がグラウンド外に(注:ノーバウンドで)出た場合、あるいは一塁または三塁の線外へ出た場合はファウルである。
引用元:野球審判員マニュアル
なんと!「ノーバウンドでグラウンドの外に出たらファール」という鬼ルール!今なら誰もが「ホームラーーーン!!」って叫ぶところですが、当時は「はい、ファールです〜」で終わり(笑)
1845年の野球では、“遠くに飛ばす”より“フェアゾーンに転がす”が重視されてたのでしょうね。パワーヒッター泣かせのルールです。
\この場合はホームランなのか?/
第11条 三振でもボール落としたらチャンスや!

第11条 投球を3回空振りして最後の投球が捕えられたらアウトとなる。捕えられなければフェアとみなされ、打者は走らなければならない。
引用元:野球審判員マニュアル
投球を3回空振りして、最後の球を捕手がしっかり捕えたらアウト。でも、もし取り損ねたら、それはフェア扱い!
これは、今でも続く「振り逃げ」のルール。この時代からすでにあったとは…。
\大丈夫ですか?振り逃げルール/
第12条 フライもワンバン捕球もアウトやで!

第12条 バットで打ったか、かすったボールが直接またはワンバウンドで捕えられたら打者はアウト。
引用元:野球審判員マニュアル
バットで打ったボールが、ノーバウンドで直接キャッチされれば、打者はアウト。これは今も同じです。
しかし、1845年のルールは違います。ワンバウンドでキャッチされても、打者はアウト!初心者でも試合がテンポよく進んだことでしょう。
\フライを落としても打者アウト/
第13条 走者はボールタッチでアウトや!

第13条 走者は、塁につく前に塁上の野手が捕球するか、ボールでタッチすればアウト。ただし、どんな場合でもボールを走者にぶつけてはならない。
引用元:野球審判員マニュアル
走者は、塁につく前に…塁上の野手がボールを捕ってたらアウト!または、ボールでタッチされてもアウト!
まさに「タッチアウト」と「フォースアウト」の原点。「ボールをぶつけちゃダメ!」というルールも、人情味があります。
\タッチとフォースの違いを解説/
第14条 守備を妨害したら即アウトや!

第14条 守備側がボールを捕えようとするのを妨害する走者はアウト。
引用元:野球審判員マニュアル
守備側がボールを捕えようとするのを妨害する走者は、問答無用でアウト。今も昔も、守備妨害のルールは同じです。
野球を楽しむためには、フェアプレー精神は大切ですね。
第15条 スリーアウトでチェンジや!

第15条 スリー・アウトで攻守交替。
引用元:野球審判員マニュアル
スリーアウトで攻守交替は、1845年から今も変わりません。野球の基本中の基本です。
第16条 打つ順番は守らなあかんで!

第16条 打者は定められた順番で打つこと。
引用元:野球審判員マニュアル
昔もかわらず、打者は決められた順番で打つルール。「次ワシ打ちたい!」なんてワガママは、通用しません。
順番を守るのも、野球の基本ルールです。
第17条 審判が絶対や!

第17条 試合に関する紛争や異議は、すべて審判が裁定する。抗議は認められない。
引用元:野球審判員マニュアル
試合でトラブルがあっても、決めるのは審判!「今のアウトちゃうやろ!」って文句も認めません。
昔もいたんですね、文句を言う人。審判は、絶対です。
\だから高めておきたい審判スキル/
第18条 ファールは何もできまへん!

第18条 打球がファウルのときは、得点も進塁もできない。
引用元:野球審判員マニュアル
ファウル打ったら、走ってもムダ!「はいストップ!」で、点も進塁もありません。
今も昔も、ファールのルールは同じですね。
第19条 ボークすな!

第19条 投手がボークを犯したとき、走者はワン・ベース進塁できる。この走者をアウトにすることはできない。
引用元:野球審判員マニュアル
投手がヘンな動きしたらボーク!ランナーは堂々と進塁OKです。
ランナーはタダでワン・ペースをもらえるので、アウトにもできません。このルールも1845年からあったんですね。
\頻出TOP3を抑えておこう/
第20条 エンツーはあるで!

第20条 打球がバウンドしてグラウンド外に出た場合は、ワン・ベースが与えられる。
引用元:野球審判員マニュアル
打球がバウンドしてグラウンドの外に出たら、ワンベース進塁OK!いわゆる「エンタイトルツーベース」の原型です。
ホームランはファール扱いやのに、エンツーはあるっていう不思議ルール。昔の野球は、やっぱり“遊び心”が満点です。
まとめ|“遊び心”から始まった野球のルール
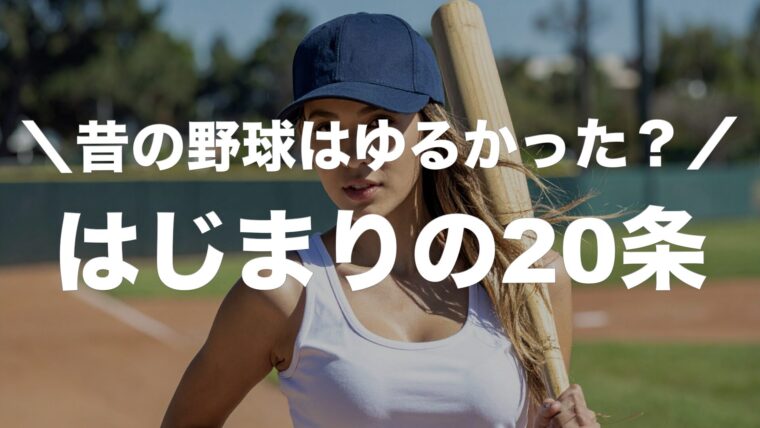
180年前の野球ルールには、今のルールの“原型”がしっかりとありました。しかも、第1条が「時間厳守で集まりなはれ」って、まるで少年野球の保護者会みたいですよね(笑)
たった20条のルールから、今では200ページを超える分厚い規則書に。それだけ野球というスポーツが、たくさんの人に愛され、磨かれてきた証拠です。
でも、どんな時代でも大事なのは「楽しむ心」。打ちやすいボールを投げて、笑いながらプレーしてた頃の“ゆるさ”も、今の野球にこそ必要なのかもしれませんね。
記事を書きながら、私自身も勉強になりました!
おまけ|参考書籍
実はこの記事、書籍「野球審判員マニュアル」を参考にしています。
ただのルールブックではなく、野球規則が 「どう生まれ、どう変わってきたのか」、“理由”や“背景”まで解説してくれる、まさに 野球ルールの教科書。
審判員だけでなく、少年野球の指導者や保護者審判にもピッタリの内容です。
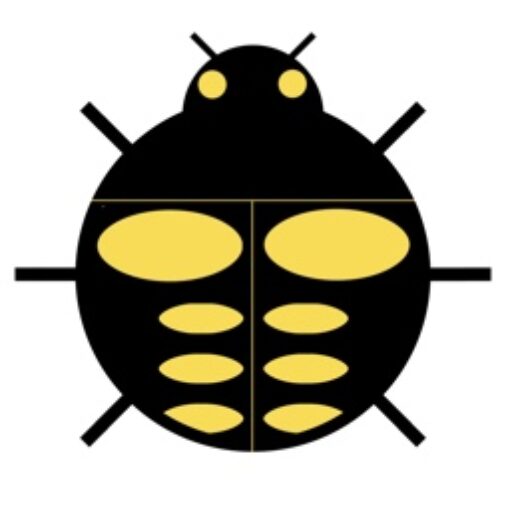
180年前の「ゆるルール」も面白いけど、今のルールを正しく理解すると、少年野球の試合がもっと楽しく見えてきます!
以上、この記事が参考になれば、うれしいです^ ^