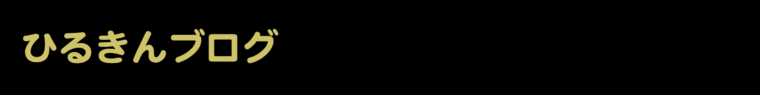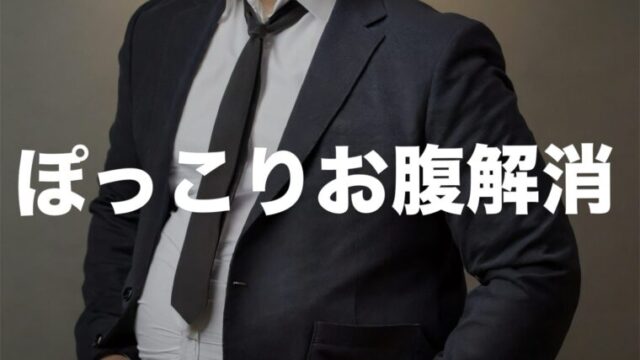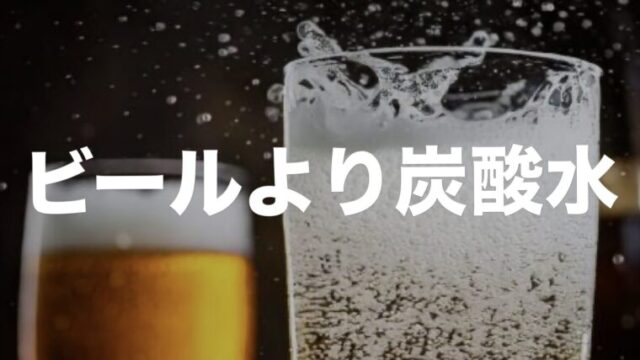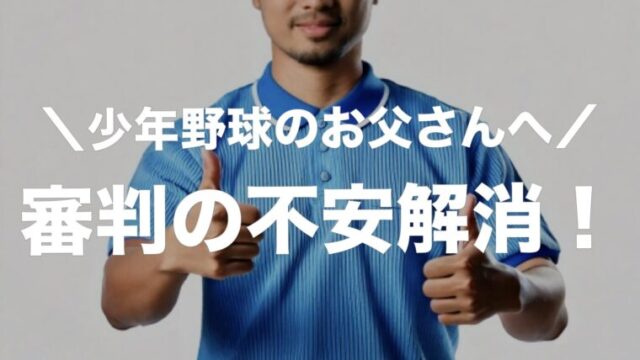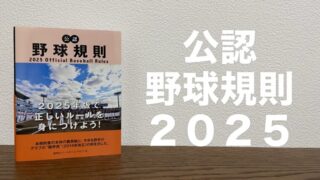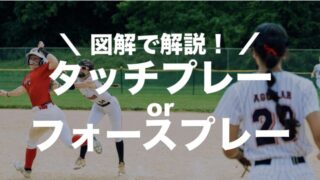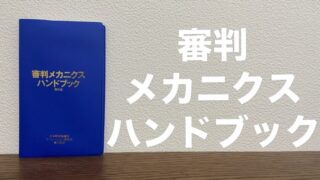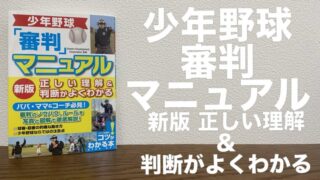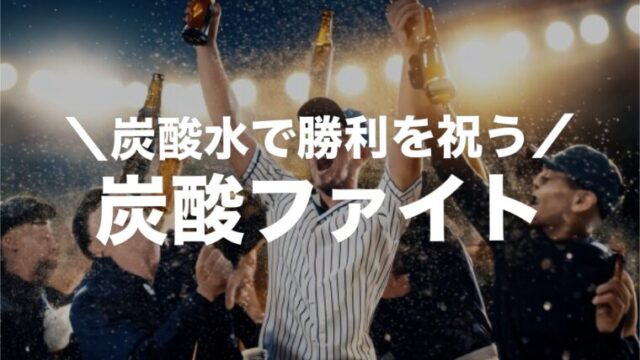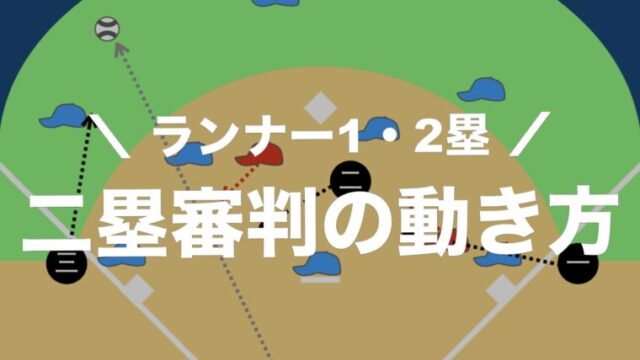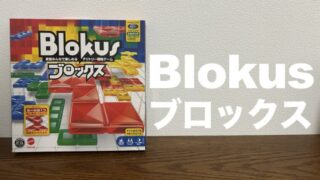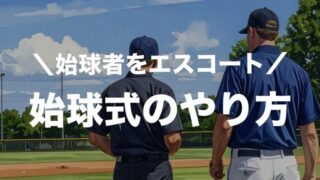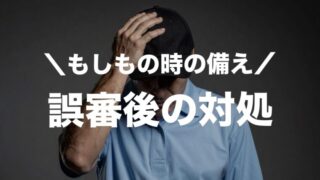【審判体験記】振り逃げを正しくジャッジ!判定に迷わないためのルール徹底ガイド
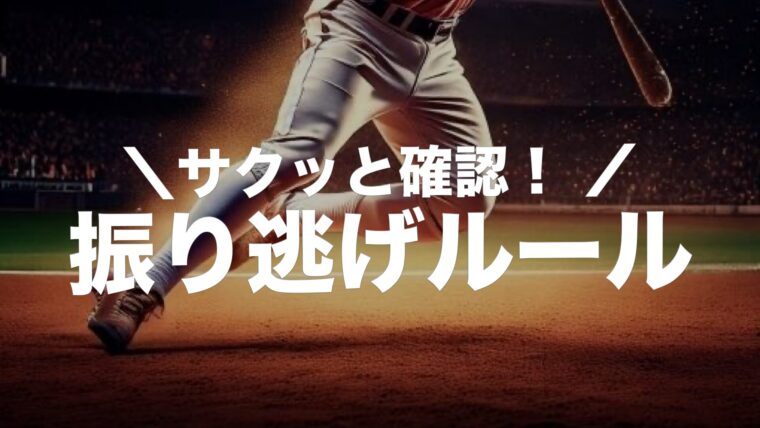
最近、少年野球の審判をすることが増えたアラフォーの「ひるきん」です。
何試合か審判を経験しているものの、振り逃げを宣告した経験はほとんどありません。さらに、振り逃げを知っているものの、細かなルールは…。
…ということで、この記事では来るべき場面に備えて、振り逃げが成立する条件を整理しておこうと思います。次の試合で振り逃げを宣告しようと思っている「お父さん審判」のお役に立てばうれしいです。
\私も公式ルールを勉強中!/
それでは、プレイボール!
\この記事を書いた人/
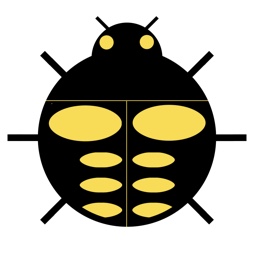
ひるきん
小学校から大学まで野球を続けた経験を持つアラフォーパパ。わが子も少年野球を始めたことがきっかけで、審判としてグラウンドに立つ機会が増えました。しかし、そこで気付かされた「野球のルール、ちゃんと分かってない…」。わが子とともに日々野球の勉強中です!
>>さらに詳しいプロフィールを見る
\こんな記事も書いています/
1つのケースだけではない「振り逃げ」

「よし、三振!」と思った瞬間、ボールを後ろにそらしてしまったキャッチャー。それに気づいたバッターは、すかさず一塁へ走り出し、セーフ。
少年野球の試合を見ていると、こういった振り逃げのシーンに出くわすこと、ありますよね。実は振り逃げが成立するケースって、これだけじゃないんです。
審判をしていると、
- 「今のは…走っていいの?」
- 「アウトでいいよね?」
と迷ってしまうことも…。
だからこそ、試合前から振り逃げが成立する条件を整理しておくことが大切。しっかり理解しておけば、いざというときも落ち着いてジャッジできます。
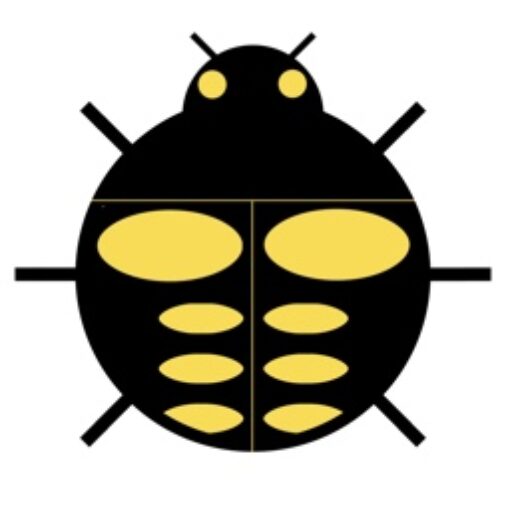
テストと同じく、審判も予習が大事です!
そもそも「振り逃げ」とは?

「三振したのに何で走っていいの?」と思ったことはありませんか?
実はこれ、公認野球規則で「バッターが空振り三振しても、キャッチャーがちゃんと捕れなかったら、一塁へ走っていいよ」と認められているプレーなんです。
- 必ずしも「三振=アウト」ではない
- 「振り逃げ=フェアボール」と同じ
必ずしも「三振=アウト」ではない
「三振=アウト」と思いがちですが、特定の条件がそろうと、三振してもアウトにならないことがあります。それが、振り逃げ。
細かなルールを習得するため、まずは正式な打者アウトの規定を見てみましょう。公認野球規則では、打者がアウトとなるケースとして、次の場合を規定しています。
第3ストライクと宣告された投球を、捕手が正規に捕球した場合。
引用元:公認野球規則 5.09(a)(2)
この規定に反する場合、打者アウトとはならず、振り逃げが成立することになります。
「振り逃げ=フェアボール」と同じ
「振り逃げ」が成立すると、打者は走者になることが許されます。公認野球規則では、打者が走者となるケースとして、次の場合を規定しています。
(A)走者が一塁にいないとき、(B)走者が一塁にいても2アウトのとき、捕手が第3ストライクと宣告された投球を捕らえなかった場合。
引用元:公認野球規則 5.05(a)(2)
この規定により、走者となった打者は、一塁をめざして走ります。
対して、守備側はアウトにしようと送球やタッチ行うため、フェアボールを打ったのと同様の展開になるのです。
\振り逃げのルールを押さえましょう/
「振り逃げ」の成立条件

意外と細かなルールがある振り逃げ。審判としてグラウンドに立つとき、「どんなときに成立するんだっけ?」と迷わないよう、2つの条件を覚えておくのがポイントです。
- 一塁が空いていること or 2アウトであること
- 第三ストライクが「正規に捕球」されていないこと
条件①:一塁が空いていること or 2アウトであること
振り逃げが成立するかどうかで、まず見るべきなのは一塁ランナーの有無とアウトカウントです。
一塁にランナーがいないなら、振り逃げOK!
これはわかりやすいですね。空いている一塁に向けて、打者は走ることができます。
一塁にランナーがいても「2アウト」なら、振り逃げOK!
0アウトや1アウトのときは、一塁にランナーがいる場合、振り逃げはできません。ただし、2アウトの場合に限り、一塁にランナーがいても振り逃げできます!
ここはしっかりと押さえて起きたいポイントです。
条件②:第三ストライクが「正規に捕球」されていないこと
もう一つの条件は、キャッチャーがちゃんとボールを捕ったかどうかが重要になります。
「正規の捕球」ってどういう意味?
公認野球規則で規定される「正規の捕球」を簡単にまとると、以下のように表すことができます。
- ボールがノーバウンドで捕手のミットに収まること
- なおかつ、確実に保持されたこと
これに対し、キャッチするまでにワンバウンドしてしまったり、ボールがミットからこぼれたりすると、「正規の捕球ではない」と判断されます。
- ワンバウンドのボールをキャッチャーがそのままつかんだ場合
- ボールがキャッチャーのマスクやプロテクターに当たって止まった場合
- ボールが球審に当たって跳ね返ってきたのを捕手がつかんだ場合
- ボールをつかんだ後にポロリとこぼしてしまった場合
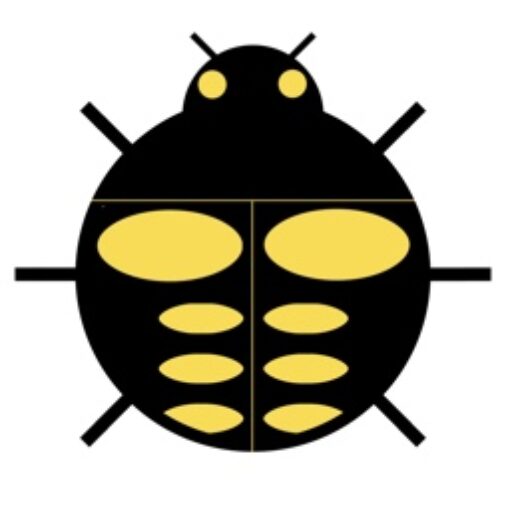
バッターがバットを振らなくても、振り逃げは成立するので、要注意!
「振り逃げ」を判定するポイント

いざ振り逃げの場面が来たとき、審判としてどう判断すればいいのか?
大切なのは、3つの状況確認を確実に押さえておくことです。一瞬のプレーでも、事前に意識しておけば落ち着いてジャッジできるはずです。
- アウトカウント
- 一塁ランナーの有無
- 捕手の捕球状況
① アウトカウントを確認する
まず見るべきはアウトカウント。振り逃げに関係するのは、主に2アウトか、それ以外かです。
- 常に振り逃げが成立する可能性あり!
一塁にランナーがいても、2アウトであれば振り逃げは成立します。2アウトでバッターが2ストライクと追い込まれたときは、必ず振り逃げを意識しておきましょう。
- 一塁ランナーの有無を確認しましょう。
② 一塁ランナーの有無を確認する
0アウトまたは1アウトのときは、一塁ランナーの有無がカギになります。
- 一塁ランナーがいないなら、振り逃げOK!
- 一塁ランナーがいるなら、振り逃げNG!
この判断を誤ると、打者走者が走っているのに「アウト!」とコールしてしまう可能性も。落ち着いて、一塁にランナーがいるか、頭に入れておきましょう。
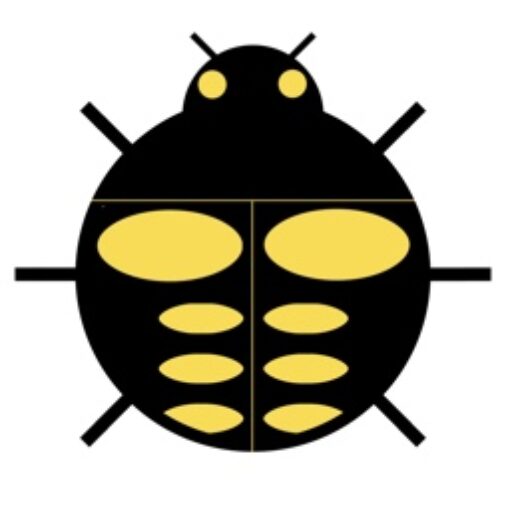
ちなみに、2アウトのときはこの確認は不要です。
③ 捕手の捕球状況をよく見る
もう一つの大事なポイントが、捕手がちゃんとボールを捕ったかどうか。「捕ったように見えた」場面でも、実は捕球していなかった…なんてことはよくあります。
- 正規の捕球ではいないなら、振り逃げOK!
- 正規の捕球であるなら、振り逃げNG!
「正規の捕球ではない」場合、たとえ三振していても、打者は走る権利があります。審判として、キャッチャーの捕球の状況を次の観点から確認しましょう。
| 捕球状況確認のポイント | 解説 |
|---|---|
| キャッチャーはワンバウンドのボールをつかんでいないか? | 地面に一度バウンドしているので、正規の捕球ではありません。 |
| ボールがキャッチャーのマスクやプロテクターに当たって止まっていないか? | ミットでノーバウンドキャッチしていないので、正規の捕球ではありません。 |
| 球審に当たって跳ね返ったボールをつかんでいないか? | ミットでノーバウンドキャッチしていないので、正規の捕球ではありません。 |
| ボールつかんだようで、実はポロリとこぼしていないか? | 最初に保持できていないので、正規の捕球ではありません。 |
注意したい2アウト満塁時の「振り逃げ」
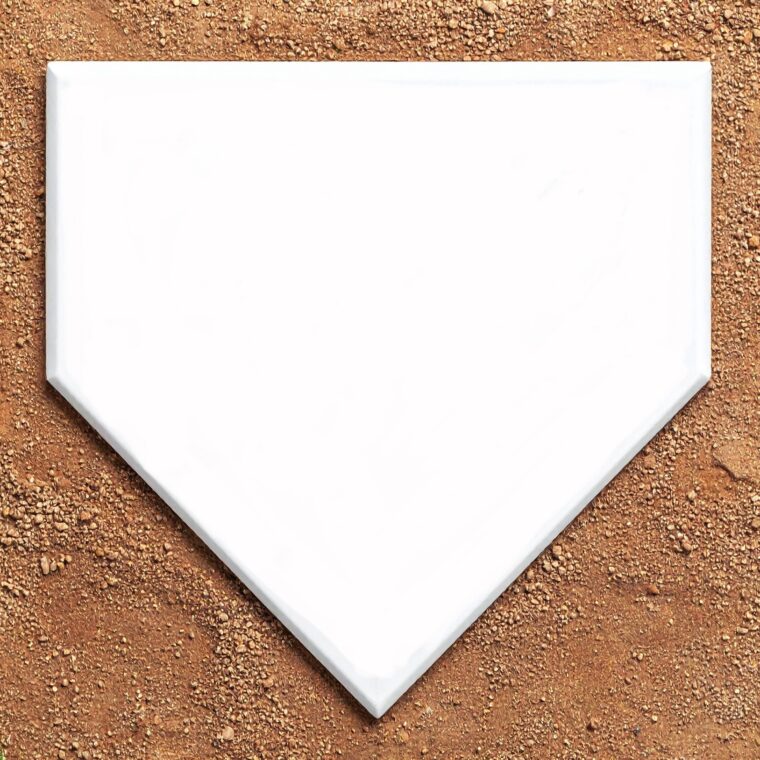
2アウト満塁の場面で振り逃げが成立すると、打者走者は一塁へ走ります。この場合、満塁のため、既に塁上にいる走者は次の塁へ押し出される形になります。

つまり、捕手は打者にタッチしたり、一塁へ送球しなくても、ホームベースを踏むだけでフォースアウトが成立するのです。
このルールは少年野球の現場では意外と知られておらず、混乱しやすいので、審判として覚えておくと安心です!
\フォースプレーとは?/
「振り逃げ」時の審判のコール例

振り逃げの場面では、審判のコールの仕方がとても大切です。ここでは、最低限おさえておきたいポイントを簡潔に紹介します。
- 基本のコールは「ストライクスリー!」
- 「バッターアウト!」のコールは要注意
- 振り逃げが成立しないとき
基本のコールは「ストライクスリー!」
「ストライクスリー!」としっかりコールするのが基本。正規に捕球されていれば、これでプレー終了です。
「バッターアウト!」のコールは要注意
ワンバウンド捕球や落球など、正規に捕球されていない場合は、「ストライクスリー!」とだけコールしてプレーを見守ります。振り逃げの可能性がある場合は、「バッターアウト」と言ってしまわないよう注意しましょう。
振り逃げが成立しないとき
一塁に走者がいて、かつアウトカウントが0または1のときは、振り逃げできません。この場合は、「ストライクスリー!」のあとに「バッターアウト!」をコールで伝えましょう。
\コールやジェスチャーが不安ならコレ!/
「振り逃げ」しない打者はアウト
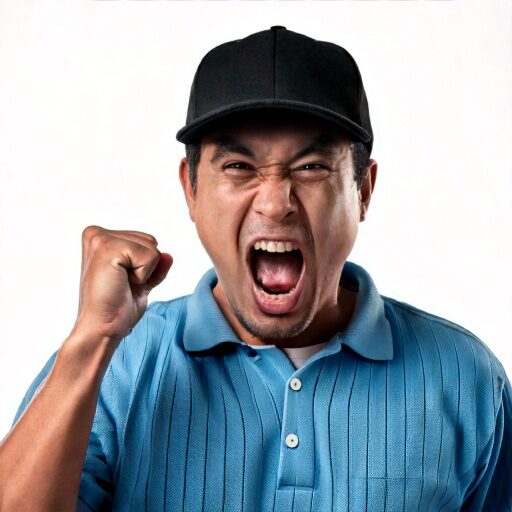
振り逃げが成立する条件がそろっていても、打者自身が一塁へ走らなければアウトになります。
打者が走る意志を見せず、ダートサークルから出てベンチに向かった場合は、バッターアウトと判定しましょう。
- 振り逃げに気づかない打者も多い
- アウト判定するポイント
振り逃げに気づかない打者も多い
キャッチャーが明らかに後ろにそらせば、打者も気づいて走りますが…
- ミットからポロッとこぼれただけ
- 捕球したけど、実はワンバウンド
…といった場面では、打者自身が振り逃げできることに気づかないこともあります。
アウト判定するポイント
振り逃げできる場面だったのに、そのままダッグアウトに戻ろうとしたときは、進塁の意思なしと判断しましょう。
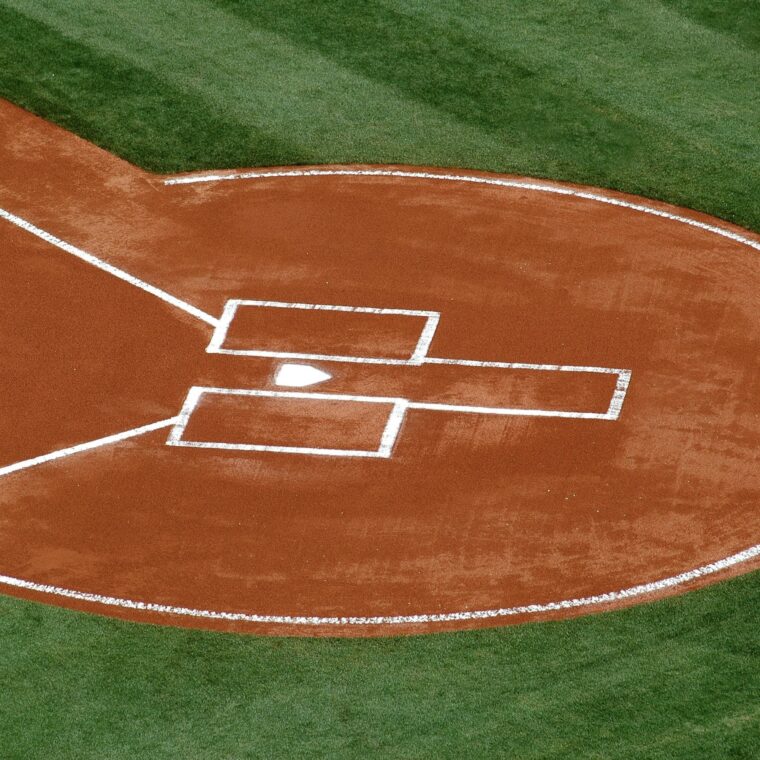
ダートサークルを出た時点で、タッチアウトを待たずにバッターアウト判定してOKです。
タッチアウトにしようとする前に、打者がホームベースを囲うダートサークルを出てしまい、打者に進する意思がなければアウトと判断する。
引用元:少年野球審判マニュアル新版
\コチラも参考になります/
「振り逃げ」のプロ野球の実例
百聞は一見に如かず。ここでは、実際のプロ野球で起こった振り逃げのシーンを3つ紹介します。
どれもルールを正しく理解していないと見逃しそうなプレーばかり。ぜひ動画で確認して、実例の知識を蓄えておきましょう!
- 振っていなくても振り逃げ成立
- ワンバウンド捕球は「正規の捕球ではない」
- 振り逃げが三塁打に!? フェアボール扱いの怖さ
振っていなくても振り逃げ成立
バッターが見逃した投球がストライクと判定されたものの、キャッチャーがボールをポロリとこぼしてしまったケース。
実はバットを振っていなくても、この状況なら打者は振り逃げできます。
ワンバウンド捕球は「正規の捕球ではない」
第3ストライクの投球をキャッチャーがしっかりつかんだように見えても、それがワンバウンドだった場合は「正規の捕球」ではありません。
この例では、ボールが地面に当たってからミットに収まったため、打者は振り逃げが認められました。
振り逃げが三塁打に!? フェアボール扱いの怖さ
空振りした投球がキャッチャーの後方に転がり、ボールを見失ってしまったことで打者が三塁まで進塁!
振り逃げはフェアボールと同じ扱いなので、守備が油断すれば一気にピンチになります。
まとめ|「振り逃げ」を判断するためのポイント
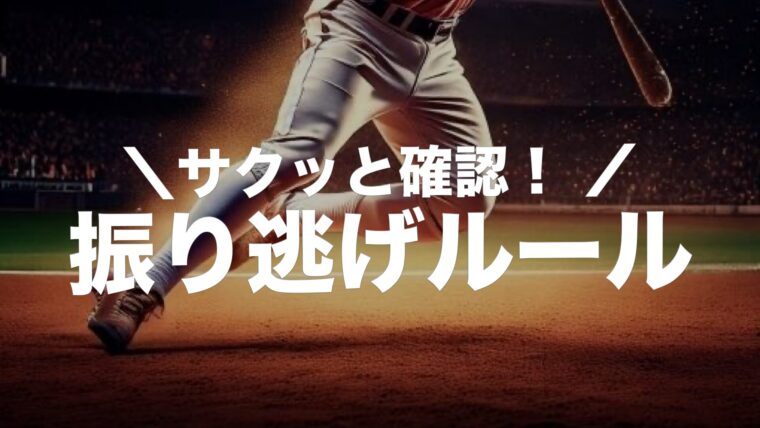
振り逃げが成立するかどうかは、以下の3つをチェック。
- アウトカウントは2アウトか?
- 0・1アウトの場合、一塁にランナーがいるか?
- キャッチャーがボールをノーバウンドでしっかり捕球したか?
この3つを押さえておけば、あとは落ち着いて判断するだけです。とくに少年野球では、選手も周りの大人も振り逃げのルールに慣れていないことが多いので、審判が自信を持って対応することがとても大事です。
私自身もまだ現場で振り逃げを宣告したことはありませんが、この記事を通してポイントが整理できました。
「次の試合ではきっと大丈夫!」そう思えるだけで、心の余裕がぜんぜん違います。
以上、この記事が審判をするパパさんたちの参考になればうれしいです^^
\こんな記事も書いています/